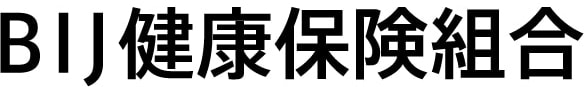今や生活に欠かせない存在となった「スマホ」。しかし、長時間使い続けると脳が疲労し、心身の不調の原因になっていることもあります。
皆さんは1日どのくらいスマホの画面を見ていますか? もしかすると、起きているプライベートな時間のほとんどを見ている人もいるかもしれませんね。
スマホは、あくまでツールです。手段であって、目的ではありません。携帯に優れたデバイスであるスマホは、知らないうちに手段から目的になりがちです。適度な距離感を保ち、使いすぎには注意しましょう。

スマホの長時間使用が脳の休息時間を奪う
脳は、目や耳などの感覚器官から送られてくる言葉や映像などの情報を処理し、体の各部へ伝える働きを担っています。多くの情報を処理すると脳は疲労しますが、通常は休息をとることで回復します。しかし近年は、仕事ではPC、それ以外はスマホと1日中デジタル機器を使い続けるケースも多く、休みなく入ってくる情報を処理し続けた結果、脳が疲弊してしまうことが増えています。
とくに機能が低下しやすいのは、「考える」「記憶する」「感情をコントロールする」といった重要な働きを担う前頭前野です。前頭前野の機能が低下すると、記憶力や集中力、判断力、発想力、意欲が低下し、この結果、単純ミスやもの忘れが増え、キレやすくなったり、抑うつになることがあります。また、自律神経も乱れることになるため、体の不調にもつながります。
気がついたら長時間スマホを使っていることが多い
仕事や家事、勉強の時間が削られている
睡眠や食事がおろそかになっている
頻繁にスマホをチェックしてしまう
家族や友人といてもスマホを見ている
上記に思い当たる人は要注意! 意識してスマホと距離を置くようにしましょう。

何もしないでボーっとする時間も大切
スマホを完全に手放すことは難しいため、使う時間/使わない時間のメリハリをもつようにしましょう。スマホを使わない時間は、脳の休息時間です。つい気になってスマホで検索したくなるかもしれませんが、脳が疲れている場合は記憶力や判断力も低下しています。いったんスマホから離れ、脳が回復してからのほうが効果的だと思うようにしましょう。
倍速で動画を視聴する、スマホを使いながら別のことをするなど、「タイパ(タイムパフォーマンス)」という新語も登場しました。いかに時間を無駄にしないか、限られた時間で情報を詰め込めるかに目がいきがちですが、一方で脳には大きな負担をかけていることになります。情報過多の現在では、何もしないでボーっとする時間も必要です。そんなとき、脳は情報処理から解き放たれ、回復しているからです。忙しいときほど、脳に休息を与えていると割り切って、何もしない時間を楽しんでみてください。脳がリフレッシュすれば、新しいアイデアも浮かんでくるかもしれません。
スマホを使う前に目的を決める(達成したらそれ以上は使わない)
寝室にはスマホを持ち込まない(目覚まし時計を使う)
家族や友人と一緒のときはスマホをさわらない(コミュニケーションを楽しむ)
など、スマホを使わない時間を決めておくとよいでしょう。自信のない人は、物理的にスマホから離れること、例えばスマホが圏外になってしまう自然のなかで過ごすキャンプやハイキング、スマホを持ち込めないサウナやスパ巡りなどを趣味にしてしまうのもおすすめです。
以前ご紹介したストレスコーピングリスト(すこやかONLINE 2020.10.15「重視すべきは質より量。MYストレスコーピングリスト」https://www.bij-kenpo.or.jp/sukoyaka/vol017/)の例も参考にしてみてください。スマホを使わず、ストレスもリセットできて一石二鳥ですよ。

スマホの時間が減るメリットに目を向けてみよう
スマホの時間が減るほど脳の休息時間が増えるため、記憶力や判断力なども通常に戻り、仕事や勉強のパフォーマンスが向上します。また、イライラも少なくなるため、ストレス解消にもつながります。
この他、就寝前のスマホをやめればブルーライトを浴びないので睡眠の質の向上に、長時間使うことをやめれば肩こりや頭痛、眼精疲労の軽減、ストレートネックの防止にもつながります。家族や友人とのコミュニケーションの機会も増え、よい関係を築くことにも一役買いそうです。
今やスマホは生活に欠かせない存在です。しかし、だからこそ健康のために使い方には注意する必要があります。健康のこと以外にも、スマホばかりを見ていたがために人生のターニングポイントを素通りしてしまったということもあるかもしれません。これは可能性の話ですが、ないとは言い切れないと思いませんか?
いずれにしても、1日中スマホなどのデジタル機器を見てばかりでは健康によくありません。意識してスマホと距離を置き、リアルな世界を楽しみましょう。
厚生労働省は、ジェネリック医薬品の利用促進のための施策に積極的に取り組んでいます。
ジェネリックに変更した場合の薬代については、日本ジェネリック製薬協会の「かんたん差額計算」(https://www.jga.gr.jp/general/easycalc.html)で調べることができます。
また、「ジェネリック医薬品希望カード」も日本ジェネリック製薬協会のサイト(https://www.jga.gr.jp/)一般の方向け情報から印刷することができます。

マイナ保険証利用のお願い
医療機関の受診時や調剤薬局ではマイナ保険証のご利用をお願いいたします。皆さんのマイナ保険証利用率の増加が、医療費の削減や健康保険組合から納付する支援金の減額に寄与します。健保財政の改善につながるよう、皆さんのご協力をお願いいたします。
●マイナンバーカードの健康保険証利用について
●2024年12月2日以降の医療の受け方について