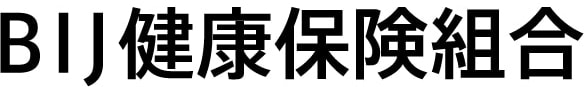※被保険者と被扶養者、いずれの出産の場合も同額が支給されます。
正常な出産は病気でないため、健康保険が使えません。代わりに健保組合は、出産育児⼀時金を支給しています(被扶養者の出産の場合は家族出産育児⼀時金として支給されます)。
2023年4月1日の出産から、政府の少子化対策強化の⼀環として出産育児⼀時金が42万円から50万円に引き上げられます。出産育児⼀時金は1994年に創設され、出産費用の増加等に伴いたびたび引き上げられてきましたが、8万円の引き上げは過去最大幅となります。
「出産育児⼀時金」支給額の変遷
1994年10月 30万円(出産育児⼀時金創設)
2006年10月 35万円(出産費用の増加)
2009年1月 38万円(産科医療補償制度創設)
2009年10月 42万円(出産費用の増加)
2023年4月 50万円(出産費用の増加)

出産には不安がつきもの。健康保険の給付について、基本的なところを押さえておきましょう。
Q 出産育児⼀時金の対象になる出産は?
A 妊娠4カ月以上(13週以上)の出産が対象となり、早産、死産、流産などの場合も含まれます。なお、帝王切開分娩など、医師による治療行為が発生する場合は健康保険が適用され、出産育児⼀時金も支給されます。
Q 出産育児⼀時金はどうやって受け取る?
A 医療機関と代理契約合意⽂書を交わす「直接支払制度」の利用が⼀般的です。直接支払制度を利用すると、健保組合が医療機関に出産育児⼀時金を直接支払うことになります。健保組合への申請は必要ありません。
ただし、BIJけんぽでは独自の給付として出産育児⼀時金にプラスして、被保険者の出産には1万円、被扶養者の出産には5 千円の付加給付を設けています。付加給付の支給には申請が必要になりますので、退院後は忘れずに手続きをしてください。
≫詳細は「出産したとき | 各種手続き」をご覧ください。
出産育児⼀時金50万円のうち、1.2万円は産科医療補償制度(出産に関連して重度脳性麻痺となった場合に補償金を支給する制度)の掛金です。このため、直接支払制度で出産費用が48.8万円を下回った場合は差額を受け取れます。付加給付と合わせて申請できます。
なお、直接支払制度を利用しなかった場合、海外での出産の場合は、窓⼝で出産費用の全額を支払い、後日、BIJけんぽに出産育児⼀時金と付加給付の申請をしてください。
※この他、受取代理制度を利用する場合は事前にBIJけんぽへの申請が必要です
Q 出産費用はいくらかかる?
A 正常な出産は健康保険が適用されないため、医療機関によって異なるのが実情です。今回の出産育児⼀時金の引き上げが決まった後、4月以降の出産費用を引き上げる医療機関が相次いだことも報道されました。医療機関を選ぶ際は、事前によく確認するようにしてください。なお、少し先の話ですが、厚生労働省では2024年4月を目途に医療機関ごとの出産費用を公表する仕組みをつくる予定です。

出産育児⼀時金以外に覚えておいてほしいことを挙げておきます。少しでも不安を解消して安心してお過ごしください。
被保険者の出産には休業補償
女性被保険者が出産のために仕事を休み、給料等をもらえなかったときは「出産手当金」が支給されます。出産の日以前42日(双子以上の場合は98日)と出産の日後56日の間、休業1日につき、標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。受給には申請が必要となりますので、忘れないようにしましょう。
≫詳細は「出産で仕事を休んだとき | 健保の給付」をご覧ください。
育休中は保険料が免除
産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中、育児休業期間中は、保険料が免除されます。なお、免除期間中も健康保険は使えますのでご安心ください。申請は事業主が行いますので、詳細は事業所の担当者にご確認ください。
出産・子育て応援ギフトがスタート
2023年1月から、妊娠・出生の届出を行った女性に自治体が計10万円分のクーポンなどを支給する「出産・子育て応援ギフト」がスタートしています。自治体によって名称、内容などが異なりますので、詳細はお住まいの自治体へご確認ください。
厚生労働省は、ジェネリック医薬品の利用促進のための施策に積極的に取り組んでいます。
「ジェネリック医薬品お願いカード」は、日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会のホームページ(http://www.generic.gr.jp/)からダウンロードすることができます。また、ジェネリックに変更した場合の薬代については、Genecal(http://www.genecal.jp/)のサイトで調べることができます。