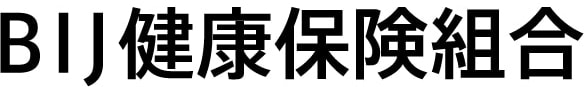最高気温が35℃を超える日を気象庁は「猛暑日」と定義していますが、記録的な暑さが続く中、より効果的に暑さを伝えられるよう、2022年に日本気象協会が40℃を超える日を「酷暑日」と命名しました。
2023年は異常気象ともいえる記録的猛暑に見舞われ、5月から9月の5か月間で、熱中症とその疑いによる搬送者は9万1,000人にのぼりました。2024年も、〝暑すぎる夏〟になることが予想されています。熱中症対策を心がけ、安全に夏をすごしましょう。

熱中症特別警戒アラート=過去に例のない危険な暑さ
高温多湿な環境に体が適応できず、体内に熱がこもってめまいや頭痛、意識障害などを起こすことを熱中症といいます。最悪の場合、命にもかかわる危険な状態です。
環境省と気象庁は、気温、湿度、日射・放射、風の要素をもとに算出した「暑さ指数(WBGT)」を活用し、熱中症リスクの注意喚起を行っています。暑さ指数が33に達することが予想される場合に「熱中症警戒アラート」が発表されていますが、2024年4月からその一段階上、「熱中症“特別”警戒アラート」の運用が始まりました。
熱中症“特別”警戒アラートは、都道府県内のすべての地点で暑さ指数が35に達することが予想される場合に発表されます。2024年6月28日現在、過去この基準に該当したケースはなく、発表された場合は〝過去最高の暑さ〟となる可能性が高いということです。人の健康に重大な被害をもたらすおそれがありますので、外出は控え、涼しい場所で過ごすようにしましょう。
クーリングシェルター

地方自治体は、役所庁舎や公民館、図書館などの公的施設のほか、ショッピングセンターなどの民間施設を誰もが休息に利用できる「クーリングシェルター」として指定しています。左のマークが該当施設なので、外出時の暑さしのぎに活用しましょう。

汗をかくことを習慣にすると、暑さに強くなる
体を暑さに順応させることを「暑熱順化」といいます。ふだんから運動や仕事、入浴などにより汗をかく習慣があると、発汗量や皮膚近くの血流量が増加し、発汗による気化熱や体の表面から熱を逃がす熱放散がしやすくなります。
暑熱順化ができていると…
皮膚近くに血液が集まり、熱を逃がしやすい!
熱中症リスク「低」
暑熱順化ができていないと…
皮膚近くに血液が集まらず、熱を逃がしにくい!
熱中症リスク「高」
暑熱順化には有酸素運動や筋トレ・ストレッチ、そしてお風呂に浸かることが有効です。ただし、身体が暑熱順化できるようになるまでに数日~2週間程度かかる一方で、涼しい環境で4日以上過ごすと、暑熱順化の喪失が始まってしまいます。定期的に汗をかくようにしましょう。
熱中症予防には
手のひら冷却も効果的
手のひらや足の裏、頬などには、動脈と静脈をつなぐ動静脈吻合(AVA)という特別な血管があります。通常は閉じていますが、体温が上がるとAVAが開き、一度に多くの血液が流れて熱が放出されます。AVAを冷やすと、そこで冷やされた血液によって効果的に深部体温(体の内部の温度)を下げることにつながります。
しかし、冷やしすぎるとAVAが閉じてしまうため、15℃くらい(保冷剤などで少し冷やした水道水に手足を浸す、専用のグッズを活用するなど)で冷やしましょう。

熱中症かも…と思ったら無理をしない
熱中症の多くは、軽症のうちに対処すれば重症化せずに済みます。めまい、立ちくらみ、筋肉痛、こむら返り、汗がとまらないなどの異変を感じたら、すぐに涼しい場所に移動して体(首の周りや脇の下、足の付け根など)を冷やし、スポーツドリンクなどをとって休んでください。水分をとっても体調が回復しないようなときは、病院を受診しましょう。
熱中症が疑われる人を見かけたとき、自力で水が飲めない、応答がおかしい場合は、ためらわずに救急車を呼んでください!!
実は熱中症がもっとも多い、住宅
熱中症の発生場所としてもっとも多いのが住宅です。高温多湿になりやすい浴室や洗面所、台所では長時間過ごすことのないようにしましょう。エアコンは我慢せずに使用し、室内であっても水分をこまめに摂取しましょう。のどの渇きを感じにくい高齢者や子どもは、「1時間ごと」など時間を決めるとよいでしょう。
厚生労働省は、ジェネリック医薬品の利用促進のための施策に積極的に取り組んでいます。
「ジェネリック医薬品お願いカード」は、日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会のホームページ(http://www.generic.gr.jp/)からダウンロードすることができます。また、ジェネリックに変更した場合の薬代については、Genecal(http://www.genecal.jp/)のサイトで調べることができます。

マイナ保険証利用のお願い
医療機関の受診時や調剤薬局ではマイナ保険証のご利用をお願いいたします。皆さんのマイナ保険証利用率の増加が、医療費の削減や健康保険組合から納付する支援金の減額に寄与します。健保財政の改善につながるよう、皆さんのご協力をお願いいたします。
使ってみよう!マイナ保険証
マイナンバーカード 「いま」と「これから」